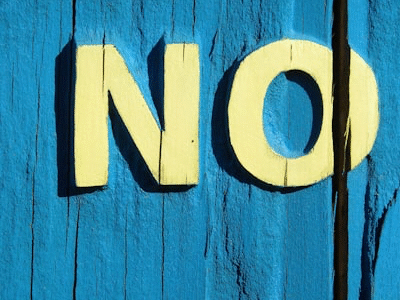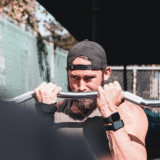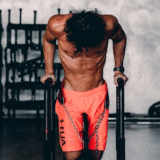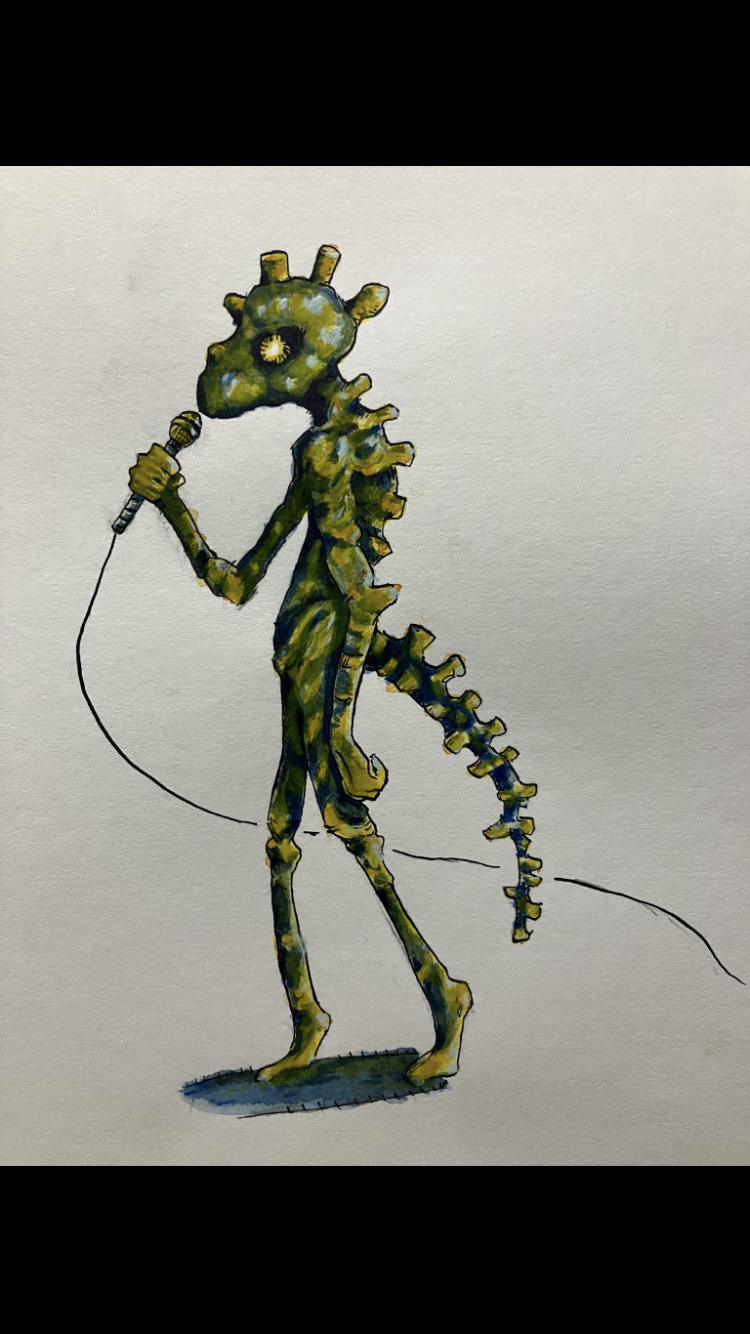
ベンチプレスのバリエーションが知りたい!!

みんな色々なやり方でベンチプレスやってるもんね!
今回は手幅や角度を変えたベンチプレスのバリエーションを見ていこう!!
ベンチプレスは人気の種目で、マシンやダンベル、バーベルを使った種目など様々なものがあります。
今回はベンチプレスの補助種目として有効なバリエーション、手幅や角度を変えることで期待できる効果を解説していきます。
この記事でわかること
- 補助種目とは
- ベンチプレスの手幅を変える
- ベンチプレスの角度を変える
- インクラインベンチプレスの具体的なやり方
目次
補助種目とは?

スクワット、ベンチプレス、デッドリフトといったBIG3に加え、プレス、クリーンが基礎を成して、あらゆる効果的なトレーニングプログラムは組みられています。
しかし、これらの基礎となる種目のパフォーマンスに関わる特定の要素を補完し、向上させるのに有効な種目が「補助種目」で、最も大きな効果を得られる基本種目のパフォーマンス向上に役立つ種目です。
まず忘れてはいけないのが、基本種目には大きな不足があるわけではありません。
これらの基本種目は、体の構造的に自然で機能的に有用な形で、たくさんの筋肉を使いたくさんの関節を動かすことができる完成されたものです。
しかし、トレーニングを始めて数ヶ月などトレーニングを一定期間続けていると、基本種目だけを行って得られる刺激では十分なストレスにならなくなります。
こういうことが起こるのは基本種目に問題があるわけでなく、基本種目におけるストレスにトレーニーの体が適応していくからです。(初めは強烈な筋肉痛を感じていたけど、全然筋肉痛にならなくなったという経験ありますよね?)
トレーニングを行う理由はトレーニング効果を得るためですが、体の適応が進むと体つきの変化もゆっくりになります。
マシンを使わない

ここで解説する補助種目ではマシンは使用しません。
ジムでよく見かけるマシンにはインクライン・デクラインベンチプレスなど様々な機能があり、胸の頂点よりも低いところまでバーを下ろせる事が可能で、本来よりも深い位置まで肘を引く事ができるタイプもあります。
片側ずつ動かす事ができるタイプもあり、ダンベルのような動きができるものもあります。
しかしベンチプレスの補助種目としてはオススメできません。
ベンチプレスというトレーニングに価値があるのは、高重量を扱えるのに加え、運動をコントロールするというバーベルトレーニングの特徴があるからです。
これらのマシンにはこの利点がありません。
ベンチプレスのバリエーション種目で価値があるのは、この利点を損なうことなくベンチプレスの動作で不足する部分を補えものです。
大きく分けて「バーベルを握る手幅を変える」「プレス動作での肩の角度を変える」2種類があります。
手幅を変える

ベンチプレスのバリエーションに手幅を変える方法があります。
グリップについては大きく2つ
- ナローグリップ
- ワイドグリップ
それぞれの特徴について見ていきましょう。
ナローグリップ
上腕三等筋を鍛えたい場合はナローグリップが有効です。
どうして上腕三頭筋が強く働くのでしょうか?
ベンチプレスの動作において、手幅を狭くするとボトムの位置で前腕が体の中心に向かって傾きます。
ナローグリップでは、バーベルをあげた位置までの移動距離は長くなりますが、バーベルを胸へ下ろしていく早い段階で肘が止まるため、肩まわりの動きが小さくなります。
バーベルを下ろすときに上腕骨の動く角度が小さくなるほど、胸の筋肉の行う仕事は小さくなり、肘の角度が大きく開閉するほど上腕三頭筋の行う仕事が大きくなります。
肘を開く角度が大きくなると、上腕三頭筋への刺激が強くなるのです。
ナローグリップで大きな効果を得るためには、できる限り手幅を狭くとることになりこれには柔軟性が影響します。
一般的なシャフトではローレットの間に40〜43㎝の間隔があるので、ローレットの内側の端を握る手幅を試してみましょう。
ベンチプレスの1RMの50%程度の重量に設定し、ローレットの内側の端に人差し指を合わせるように握ります。通常のベンチプレスのように呼吸をし、背中の姿勢をし、足の位置をきめ、胸を張って同じように挙上動作を行います。
1セットを終えたら、指1本文だけ手幅を狭くして1セット行います。
1セットあたり5レップで、セットごとに指1本ずつ手幅を狭くしていきます。ボトム位置で手首がつらくなりはじめたら、指1本分だけ外に広げ直しましょう。
重量が伸びてきたらそれに合わせて手幅を広げていきます。軽い重量では問題なかった手幅も重量が大きくなると痛みが出ることがあります。
ナローベンチプレスは高回数の設定で行われることが多いですが、これは単にそうしてきた人が多いというわけで高回数でなければならない理由はありません。
通常の手幅よりも軽い重量を使うので、通常のベンチプレスのあとに行うこともできますし、別の日に軽い重量として取り入れることもできます。
- 使用重量が下がる
- 特定の筋肉への刺激が減る
1 使用重量が下がる
通常の手幅と比べてボトム位置での大胸筋と三角筋の働きが弱まる影響で扱える重量が、通常よりもやや小さくなりがちになります。
ワイドグリップと比べると、バーベルの移動距離の影響に加えて大胸筋と三角筋の働きが弱まる影響で大きな重量をあげるとう意味ではずっと不利になります。
2 特定の筋肉への刺激が減る
ナローベンチプレスでは上腕三頭筋が強く働き、大胸筋と三角筋の働きは弱まります。

上半身の筋肥大という面では、通料の手幅でのベンチプレスの方が有効だよ
ナローベンチプレスは通常の手幅と比べて握りが安定しないので、バーベルをしっかり握る意識が特に重要。
バーベルを押し上げる動作の途中で手首がブレるとバーベルを落としてしまうことがあるのです。
またナローベンチプレスは、いきなりバーベルをあげられなくなる事が多いことで知られています!限界に到達してバーベルを挙げきれなくなることが前のレップで感じとりにくいという事です。

一般的に言えることとして、動作に動員される筋量や筋群の数が少ないトレーニング種目では、多くの筋肉を動員する種目に比べて、突然限界に達して挙げられなくなる傾向があるんだ!
突然限界がきて上がらなくなっても大丈夫なように、安全バーは必ず設置するようにしよう!
ワイドグリップ
ワイドグリップベンチではバーベルの移動距離が短くなりますが、大きな重量を扱う事ができます。
通常の手幅ではボトム位置で前腕が鉛直になり、肘の移動距離が最も大きくなりますが、手幅を大きく広げると肘とバーベルの移動距離が短くなります。
これはバーベルが胸に触れるまでに肘があまり下に動く余地がなくなるからです。
上腕三頭筋が肘を伸ばす範囲が小さくなり、バーベルを動かす仕事は大胸筋と三角筋が主に行うことになります
バーベルの移動距離が短いので大きな重量を扱うことができ、その重量を上げるのに上腕三頭筋があまり働かないので、主に大胸筋が仕事をする形になります
大胸筋と三角筋が主に働くの上腕三頭筋の関与が減ります。
上腕三頭筋の働きが小さくなり大胸筋と三角筋に最も強く頼る形となります。
上半身全体を均等に鍛えたいのであれば、通常の手幅のベンチプレスを行った方が効率的と言えます。
角度を変える

『ベンチプレスを行うベンチの角度を変える』
ベンチプレス時の背中の角度によって、大胸筋と三角筋の動員のされ方が変わります。
ベンチプレスの角度の変化には2通りの方法があり、股関節よりも肩を低い位置に下げるデクラインと、股関節よりも肩を高い位置に上げるインクラインがあります。
デクラインベンチプレス
デクラインベンチプレスとは、肩の位置を股関節の位置よりも低い位置に下げて行うベンチプレスのことをいいます。
デクラインプレスの背中の角度ではバーベルの移動距離が短くなり仕事量が減るので、大きな重量を扱うことができるようになり、大胸筋の下部を鍛えるのに有効な種目です。
デクラインプレスはより大きな重量を扱う事ができますが、角度を変えて、移動距離を制限していることを忘れてはいけません。
またデクラインプレスでは胸骨下部にバーを下ろし損ねると、次にバーを受け止めるのが喉になるので注意が必要です。

大胸筋下部を狙ってトレーニングしたい場合は、ディップスを取り入れる方が効果的です。
ディップスはより多くの筋肉を動員し、バランスと身体の動きを協調することが必要になり、神経系の活動も高くなります。
インクラインベンチ
大胸筋の上部に特化したトレーニングがインクラインベンチプレスです。
基本的にベンチプレスとプレスの両方を行っていれば、肩と胸のトレーニングで不足する部分はありません。大胸筋上部はプレスで少なからず動員され、ベンチプレスでは大胸筋全体が動員されます。
しかし「多くのスポーツ場面では胸に対して90°よりも高い位置で腕を使う場面があり、強化する必要があること」や、「大胸筋上部の筋肉をより肥大させる」
インクラインプレスではそれが可能になります。
インクラインベンチでは簡単にチーティングが出来てしまい、チーティングを行うとインクラインで行う意味がなくなってしまいます。
最もよくあるのが、ベンチからお尻を浮かせて体幹を水平に近づけ、インクラインの角度がなくなってしまうことです。
インクラインベンチプレスは補助種目です。
インクラインベンチプレスで大切なのは自分でコントロールできる重量を使い、お尻を上げずに角度を保ってトレーニングすることです。
ベンチの角度が立ちすぎる、寝かせすぎる
インクラインベンチプレスの背中の角度は30°〜45°で行います。
この角度から寝かせるとベンチプレスに近づきすぎ、これよりも立てるととプレス近づきすぎます。
角度を立て過ぎてプレスに近い角度になると、肩に非常に負担の大きな角度で背中が固定されることが問題となります。
プレスでは限界に近いレップ行うとき、自然と背中の角度を調整しストレスを逃がすことができますが、背中が固定されていると、肩が疲労した状態で過度の負担がかかることがあります。

角度を変える際はベンチに表記してある角度をしっかりと確認するようにしましょう。
インクラインベンチプレスのやり方

セッティング
インクラインベンチでは、背中の角度を地面に対して垂直から30〜45°ほど寝かせるように設定します。
バーベルをラックに載せる高さは、少し肘を伸ばすだけでバーベルをラックから外すことができる高さ。ラックに載せたバーベルに手を掛けると肘がほぼまっすぐ伸びた状態になり、肘を完全に伸ばすとバーベルがフックの5㎝ほど上に挙がり、フックを超える高さが目安になります。
フックの位置が低すぎると、バーベルをラックから外すのに多くのエネルギーを奪われることになり、高すぎると、疲れてバーベルを戻せないときに手間がかかる可能性があるので注意が必要です。
適切な高さはベンチによって変わるので、実際に試してやりやすい設定を探すことが必要になります。

スタート位置ではバーベルは胸の上で肘をまっすぐ伸ばした状態。
ベンチプレスと同じように、腕が地面に対して垂直で、バーベルが肩関節の真上にあるとバランスが取れます。
ただインクラインプレスでは背中に角度がつくのでラックからスタート位置までの距離が短くなり、バーベルをラックから外したり戻したりする動作をずっと楽に行うことができるよ!
基本動作
インクラインベンチとベンチプレスの違いのほとんどは背中の角度によりもので、この2種目の動作は基本的に同じです
・胸を張り、背中を引き締め、視点を定めて天井の1点を見る
(バーを見つめると安定性がなくなる)
・両足は地面をしっかりと踏ん張り、大きく吸い込んだ空気が胸を安定させる。
(両足は地面を完全につけると、けつ上げが起こりにくくなる)
・肩を寄せて引き締め、肩がベンチに触れる位置からシートの間で背中を反らせて固める。
・動作のあいだ肘はずっとバーベルの真下にあり、バーベルの軌道をコントロールする
・視点は天井の一点に定め、バーベルの動きを目で追わない
・挙上動作中は息を止め、バーベルを挙げきった位置でレップごとに息継ぎをします。
(呼吸はバルサルバ法で行う)
・バーベルの握り方はベンチプレスと同じで親指をバーベルに回して、手のひらの付け根にバーベルを載せます。
(サムレスグリップではなく、サムアラウンドグリップで握る)
・足は地面にしっかり踏ん張って、ベンチに対する姿勢を安定させます。
下ろす位置
インクラインベンチプレスにおいてバーベルの軌道はまっすぐになりますが、バーベルを下ろすのは胸骨の真ん中ではなく、顎のすぐ下の胸鎖関節(鎖骨と胸骨がつながる点)の少し下あたりになります。
バーベルの軌道はほぼ完全に鉛直になり、バーベルの移動距離はベンチプレスより少し長くなります。
肘がバーベルの真下にあると、バーベルを胸に下ろした時に肩とバーベルが一直線に並ぶようになります。上腕骨はベンチプレスのように外転90°に近づくことがないので、肩のインピンジメントは起こりません。
まとめ
ベンチプレスのバリエーションである手幅を変える方法と、背中の角度を変える方法を紹介しました。
手幅や背中の角度を変えると部分的に特化して鍛える事が可能になりますが、逆に筋肉が十分に使用されないデメリットも発生します。
効率的に上半身の筋肉を鍛えたいなら基本種目をやり込む。
その上で補助種目を行う事が筋肥大、体の機能向上では効率的であることは忘れないようにしましょう。