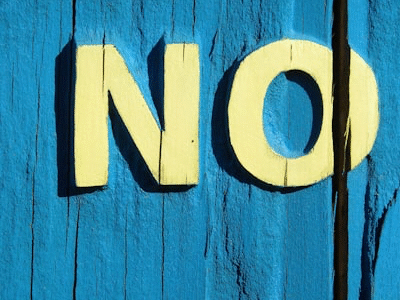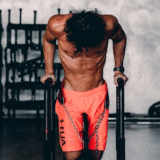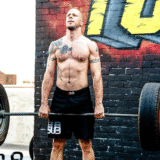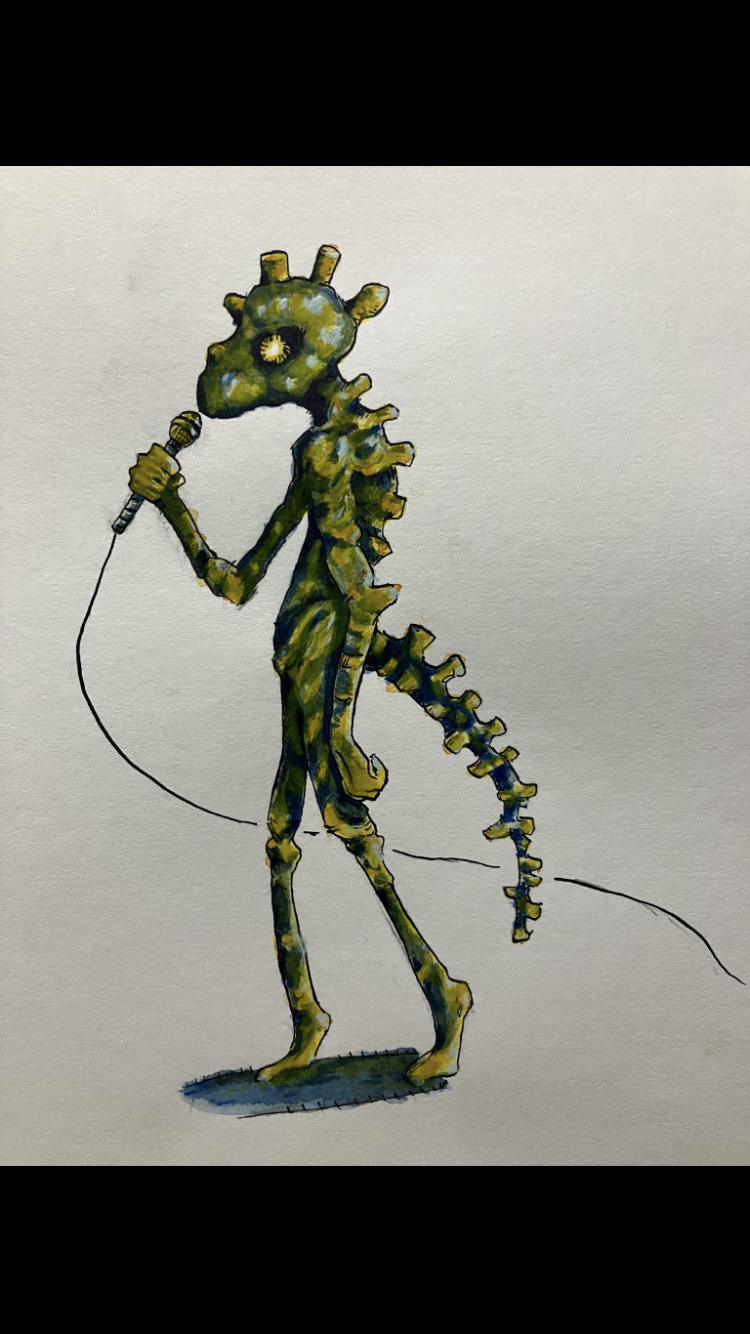
バーベルロウって難しくない?
注意した方がいいところを教えて欲しい!

バーベルロウはトレーニング種目として優秀なんだけど、フォームや使用重量の設定が難しいよね!
今回はバーベルロウの細かい解説をやっていくね!
ロウイング系の種目というとマシン種目を思い浮かべると思います。ジムではケーブルロウやロウイングマシンがたくさんあり、やっている人も多いと思います。
しかし、最も効果的なロウイング種目とは『自ら姿勢を作り、セットの終わりまで維持しなければならない種目であること』です。
マシンを使わないことは、ロウイングの動作でバーベルを動かすのに加え、背中を安定させ、ロウイングを行うのに正しい姿勢を保つ仕事も自ら行うことになり、両方の効果を得ることができます。
効果の高いバーベル種目全てに共通する事として、動作中に行わなければならない仕事が多いほど優れたバーベルトレーニング種目だと言えます。
効果的なバーベルロウのやり方を見ていきましょう。
この記事でわかること
- バーベルロウイングの効果
- デッドリフトとバーベルロウイングの違い
- バーベルロウイングのやり方
- バーベルロウイングでの間違い
目次
バーベルロウイングの効果

マシンやケーブルで行うロウイング系種目と比べて、バーベルロウイングが有能なのは、広背筋、上背部、腕といった一般的にロウイングで使われる筋肉に加えて、下背部と股関節の伸展筋群も鍛えることができる点にあります。
バーベルロウでは全てのレップがデッドリフトと同じように、地面にはじまり地面に終わります。また、レップごとに息継ぎをして下背部の姿勢をリセットするので、レップ間に腕を伸ばしてバーベルを手に下げる状態になりません。
この地面から動作を始めることにより
・ハムストリングと大臀筋を使ってバーベルを上げ始め、広背筋と肩甲骨の内転筋群を使って引き切ることができる
・大きな重量を扱うことができる
というメリットが生まれ、多くの筋肉を動員し、筋肉に強い負荷を与える事が可能になります。
デッドリフトとバーベルロウイングの違い

先ほどの説明で、「これほとんどデッドリフトじゃない?」と思った方はおそらくBIG3をやりこんでいる人でしょう。
デッドリフトとバーベルロウイングの大きな違いは、バーベルロウイングではバーベルを地面から引き上げた後、背中の角度が変わるという事にあります。
デッドリフトと違いバーベルロウイングの場合は、膝が伸展してあまり関与しておらず、股関節の伸展筋群が胸を持ち上げ、まっすぐに固定された背中を通してバーベルへと力を伝えます。
バーベルロウイングのやり方

バーベルロウイングを地面から行うときに、下背部の姿勢がフォームの最も重要な要素となります。
デッドリフトと同様に、バーベルロウイングでも腰椎の伸展を保たなければいけません。
セッティング
バーベルを引き切るところでは肘が曲がり、胸郭の下部にバーベルをぶつけます。
デッドリフトと同じように、バーベルが地面から離れる時、バーベルは肩甲骨の真下にきます。
しかし、デッドリフトのように背中が直立することはなく、肩が水平から15〜20°の位置より大きく高く上がることはありません。
バーベルに対して立ち位置を決める時は、デッドリフトと同じか少し狭い足幅(垂直にジャンプして1番力が出る位)
バーの軌道はデッドリフトで通る軌道と同じように、足の中心の真上を鉛直の軌道で動きます(土踏まずの位置)
ウォームアップで使うような軽い重量の場合、湾曲した軌道でバーベルをお腹まで引くことができますが、重量を追加していくにつれて、自分が意識していなくてもバーベルは自然と足の中心の真上に正しく位置取るようになります。
自分に合った手幅を見つけるのは調整が必要になりますが、初めのうちはベンチプレスで使う手幅から始めるのがベストです。
重量が大きくなると、握力が先に負けてしまう事が起こるのでストラップを装着するようにしましょう。
視点は自分の少し前の地面に定めます。
真下を向いてはいけませんが、真正面を向くと首を伸展させすぎてしまうことになるので、注意しましょう。
バーベルロウイングの動作
大きく息を吸い、肘をまっすぐ伸ばした状態でバーベルを地面から離します。そこから肘を曲げてバーベルを挙げていき、お腹の上部にぶつけます。
肘を天井にぶつける意識でバーベルを上げるようにする事がポイント!バーベルロウにおいて最も重要なのは背中の姿勢です。バーベルが動いている間はずっと脊柱を伸展させ、胸をはり、下背部を反らせた状態を保つ必要があります。
バーベルがお腹に触れた後はバーベルを地面に戻して息をはき、息を吸い直して背中の姿勢をリセットしてから次のレップに入ります。
バーベルをお腹まであげた位置で静止しようとしたり、バーベルをゆっくり下ろそうとすることはやめましょう。バーベルロウはデッドリフトのようにコンセントリック中心(筋肉が縮みながら力を発揮する状態)で行うものです。
股関節の伸展を使う
バーベルロウでは膝の伸展ではなく、股関節の伸展を使ってバーベルを地面から引き始める事が重要。
軽い重量では腕の力だけでロウイングを行う事ができますが、重量が大きくなるにつれて股関節を使う必要があります。
バーベルロウイングではバーベルが上がり始める前は膝は完全に伸展していないものの、ほとんどまっすぐの状態になり、股関節の位置はデッドリフトのスタート姿勢と同じで大腿四頭筋を使う余地がほとんどありません。
このため、動作の開始時には腕をまっすぐ伸ばした状態で、胸を持ち上げて背中の角度を少し立たせることでバーベルを地面から引き離します。
この動作は脊柱起立筋のアイソメトリック収縮(関節の角度を変えずに筋肉が力を発揮)により、がっちり固定された背中に対してハムストリングと大臀筋が働くことで起こります。
このように股関節の伸展が起こることでバーベルが動き始めるのです。この勢いを肘が引き継ぎ、肩の伸展と肩甲骨の内転を使ってバーベルを上げていきます。
ここでは広背筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋、前腕の筋群、三角筋後部、肩甲骨周りの細かな筋群が主導筋となり、体幹は体幹の筋群によって支えられることで安定し、力を出すための土台として機能します。
このように上半身がロウイングの動作を行っている間、動作のはじめで股関節を伸展させたハムストリングと大臀筋は骨盤、さらには下背部を安定させる働きをしています。
動作が進むにつれてそれぞれの筋肉の働きは変化しているのです。

バーベルロウでの股関節伸展筋群は、初めと終わりで違う働きしているんだね!
バーベルロウイングのバリエーション
標準的なバーベルロウのバリエーションとして、逆手でバーベルを握り上腕二頭筋の関与を高める方法がありますが、逆手のバーベルロウは、柔軟性が低い人が行うと肘への負担が大きくなるというデメリットがあります。
バーベルを逆手で握ると、上腕骨をかなり大きく外旋させた上で手を完全に回外させることになります。
大きな重量でロウイングを行うと前腕の筋肉が肘に付着する部分に負担をかけることになり、テニス肘やゴルフ肘と呼ばれる症状を短時間で招いてしまう事があるのです。
逆手のバーベルロウを取り入れる場合には、初めの1〜2回のトレーニングは軽い重量から始めて、慎重に重量を増やすようにしましょう。

順手で行う場合よりも手幅を狭くすると、逆手による問題を抑えやすくなるよ!!
バーベルロウイングにおける間違い

重量が大きすぎる
フォームを保つのが難しくなるほどの高重量でロウイングを行うのは有効ではありません。
バーベルロウイングでは重量が大きくなるにつれて、胸を落としてバーベルを迎えに行こうとする傾向が強くなります。バーベルを地面からあげ切るのではなく、上から体を動かしてレップを成立させようとしてしまうのです。
胸が大きく落ちるようなら重量が大きすぎるという事です。
『胸が大きく落ちる』というのはかなり主観的なもので、胸が落ちるのは全く許されないと考えるとバーベルロウで高重量を扱うことはできなくなります。
そのためバーベルロウでは1セットあたり5レップ以上の回数に設定しましょう(1セットあたり3レップのような重量ではそもそも正しく動作を行うことが難しくなります)
あらゆる付加種目に共通する事として、重量が大き過ぎて効果を得られなくなるより、軽めの重量でも正しいフォームでレップ数を稼ぐ方がずっと有効です。
1セットあたり5レップ、8レップ、10レップといった回数で複数セット行うのを目安に始めましょう。
レップ数をこなすにつれて上半身が疲労し、バーベルを上げるのに股関節の伸展に頼りがちになります。ここでロウイングがデッドリフトに変わってしまわないように注意しましょう。背中の角度が水平よりも大きく立ってはいけません。セット後半で胸を大きく持ち上げてしまい、お腹の低い位置にバーベルが当たるようになると対象となる筋肉を動かす動作が小さくなってしまします。

正しいフォームでロウイングを行える重量と全くロウイングの動作が行えなくなる重量の差には、7kg程度の差しかない場合がよくあるよ!
まとめ
バーベルロウイングは初心者の基本種目として取り上げられる事が多いが、実はとても難しい種目で、やり方によってはデッドリフトになってしまいます。
しかし、ケーブルやマシンを使ったトレーニングに比べて動員される筋肉量が多く、高重量を扱う事ができるというメリットもあり筋肉に強い負荷を与える事ができます。
今回あげた注意点を意識して質の高いトレーニングを行いましょう!