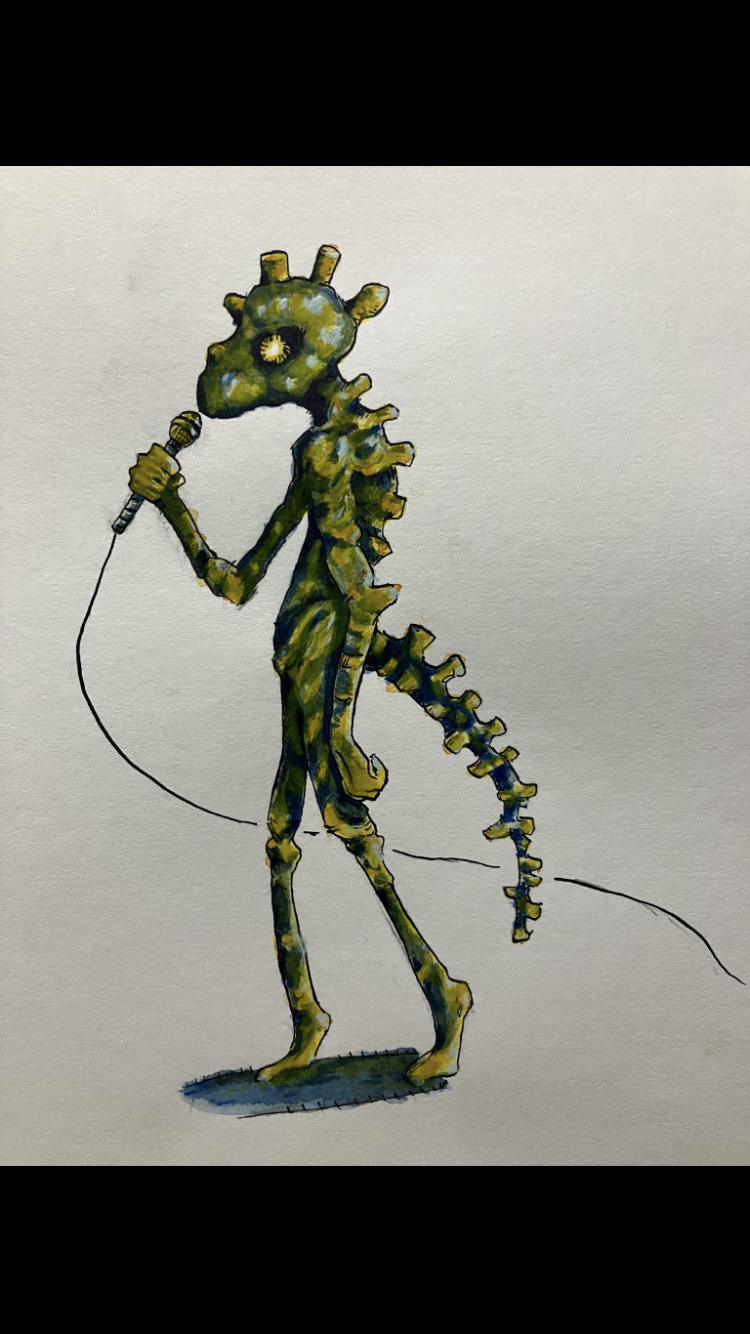
今年こそは腹筋割ったるで!!
でも、筋トレ早くも挫折しそうな予感‥
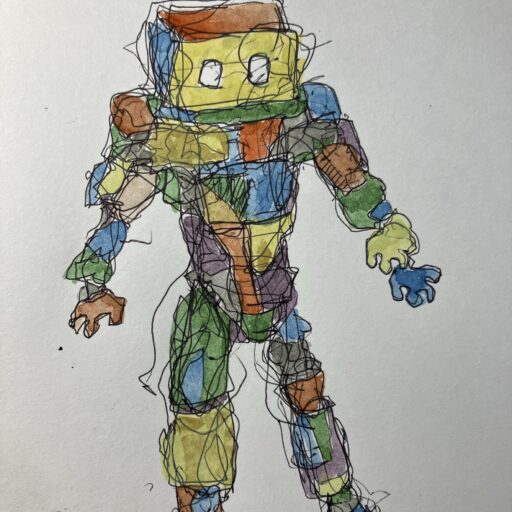
夏が近づいてきたな。
そろそろ『あの光景』が始まるぞ!!
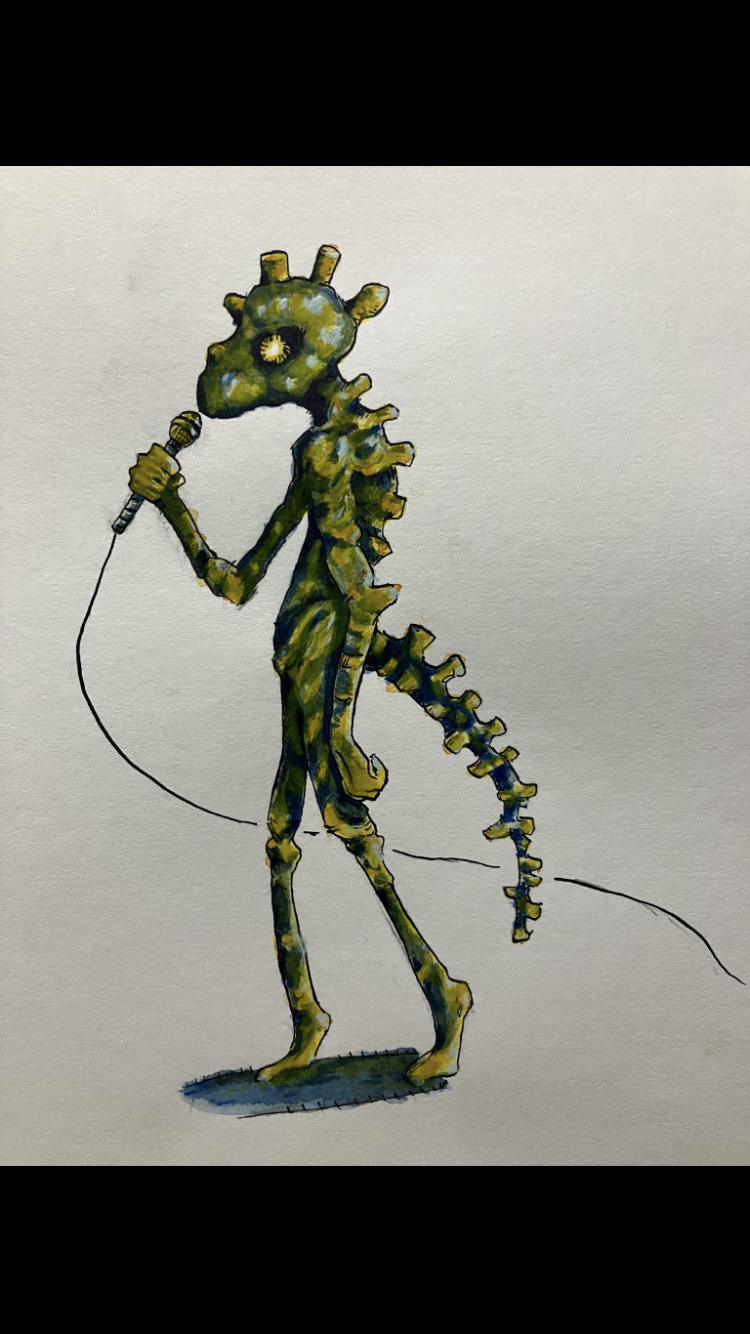
あの光景?
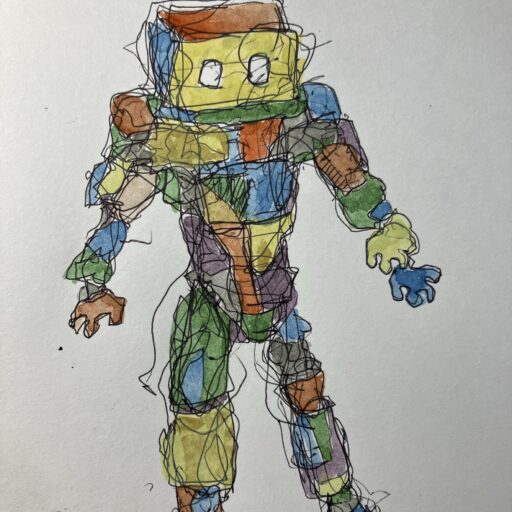
そう、夏が近くなるとジムの会員が一時的に爆増するんだ!
使えないマシーンも出てくる。
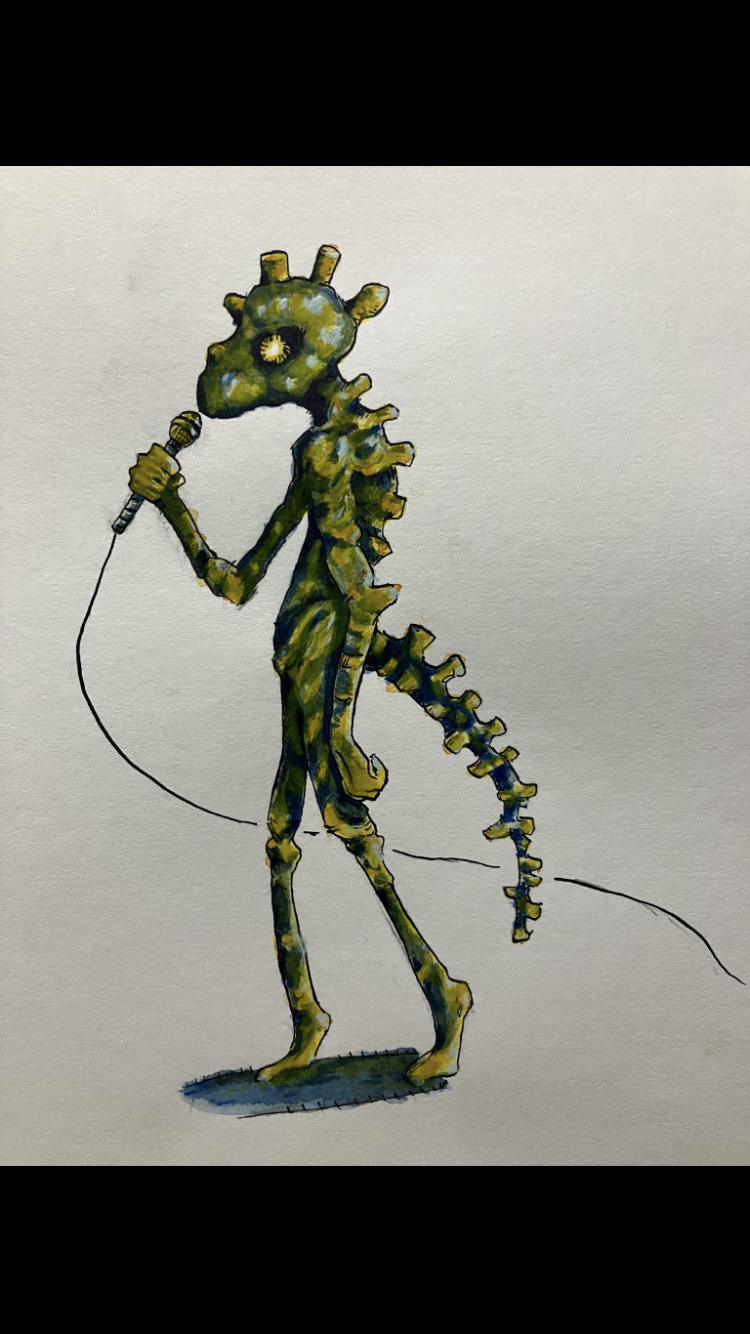
YouTubeの『ジムあるある』で見たことあるよ!
夏前になったら人が増えて、冬になったらジムがガラガラになるってやつ?
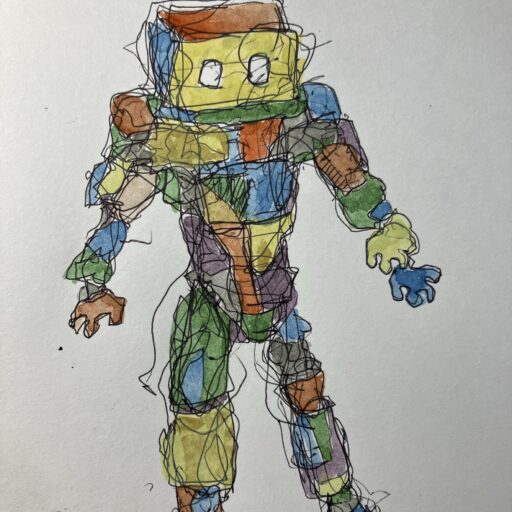
そうそう!
夏前に「今年こそは筋トレを頑張って、夏までには腹筋を割るぞ!!」と決意してジムに通うけど、夏が終わるとトレーニングしなくなってしまうっていうやつだね。
ジムでこのような光景が毎年繰り広げられるのは、『筋トレの継続率が4%』しかないためです。
実際に私自身も、筋トレに挑戦して効果を感じる事ができずに何回も挫折しており、毎年「今年こそはいい体になる」と新年の抱負で決意していました。
しかし、30歳を過ぎて筋トレを始めた筋トレ歴も今では5年以上となり、フィジークのコンテストに参加するまでに成長する事ができました。
そう、筋トレ継続にもコツがあるのです。
この記事でわかること
- 筋トレが続かない理由
- 筋トレを継続するための4つのコツ
今回は、この2つを解説していきます。
筋トレが続かない理由

Sperandei S, J Sci Med Sport, 2016によると、トレーニングジムの継続率は、開始から3ヶ月後で37%、1後にはたったの4%未満まで減少。
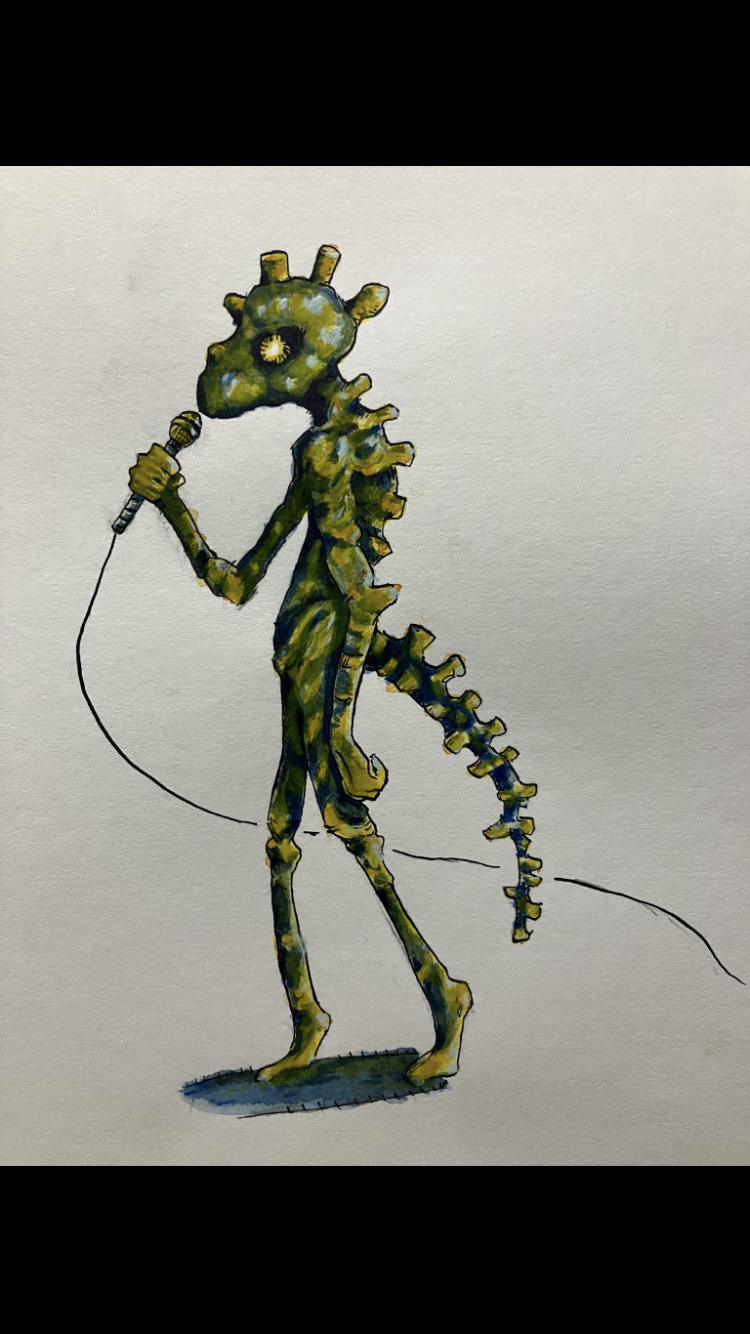
継続率低いな〜
体が適応していない
前提として、人間は進化論的・脳科学的にも筋トレを習慣化できない事が『当たり前』ということを理解する必要があります。
石器時代においてエネルギー不足は死活問題。
エネルギーが不足すると、食べ物を確保するための狩猟、天敵からの逃避、生殖活動もできなくなるという問題がありました。
筋肉は基礎エネルギー量の25%を使用するため、食べ物が少なくエネルギーが摂取できない状況では筋肉をつけることはコスパが悪いのです。
石器時代から体と心が適応してない私たちには『運動より休養を好む』システムがインプットされているようです。
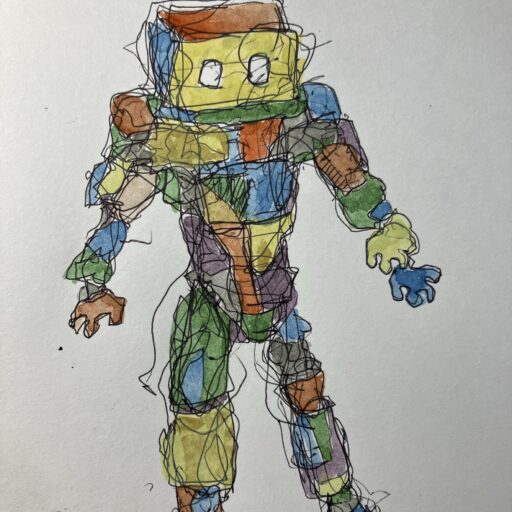
どうやら『人は筋トレをするようにデザインされておらず、筋トレが続かないのは自然であり、正常』のようです。
効果が見えにくく、時間がかかる
『効果が見えにくく、時間がかかる』というのも継続できない理由の大きな一つといえます。
初めに理解しないといけない事は、筋肉は一夕一丁でつくものではありません。
具体的に言うと
筋トレ3ヶ月後:「少し痩せた?」と言われる
筋トレ6ヶ月後:自分では筋肉がついてきたと思うけど、自分で言わないと気づかれない
筋トレ1年後:「雰囲気が変わったけど何やってるの?」と人に気づかれる
周囲から見た体の変化なんてこんなもので、周りの人から『いい体だね』と認識してもらうには、1年位かかると考えた方がいいです。
このように考えると、継続しても効果が見えにくい筋トレの継続率4%というのは納得の数字と言えます。
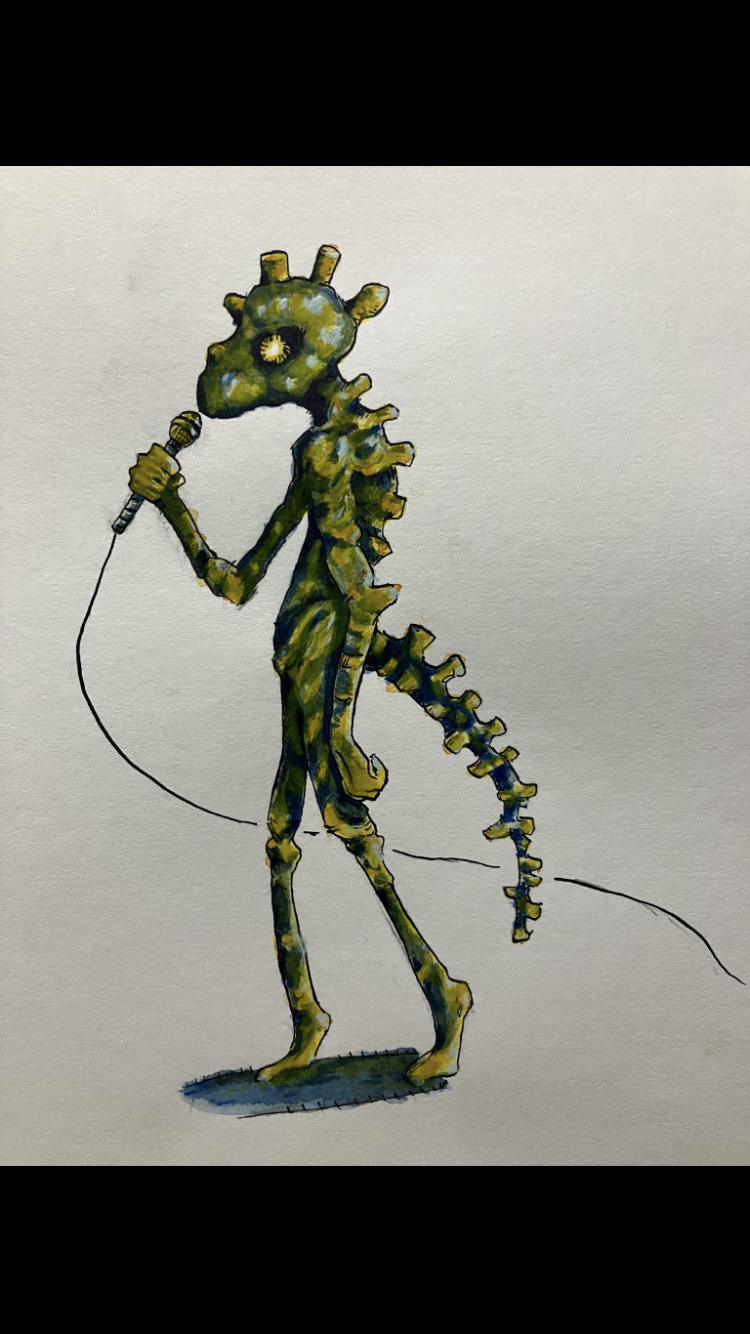
まじかよ…
でも、ライザップのCMは1ヶ月でブヨブヨの体の人が細マッチョになってるよ!!
ライザップのCMを見ると、1ヶ月で体がバキバキになっているので『筋肉はすぐにつくもの』というイメージになるのは無理もないです。
しかし、CMで流れているのは筋肉が付いて体が変わっているのではなく、運動と食事制限で身体を絞っているだけで『筋肉がついているようにみえているだけ』なので、食事制限をやめるとすぐに元の体に逆戻りします。

脂肪を落とせば誰でもバキバキの体にはなりますが、無理なダイエットはすぐにリバウンドしてしまいます。
無理のない食事制限と運動がいい体を維持するための秘訣である事は間違いないでしょう。
筋トレ継続の4つのコツ
最初の3ヶ月間は毎日筋トレをする

最初の3ヶ月は毎日筋トレしましょう!
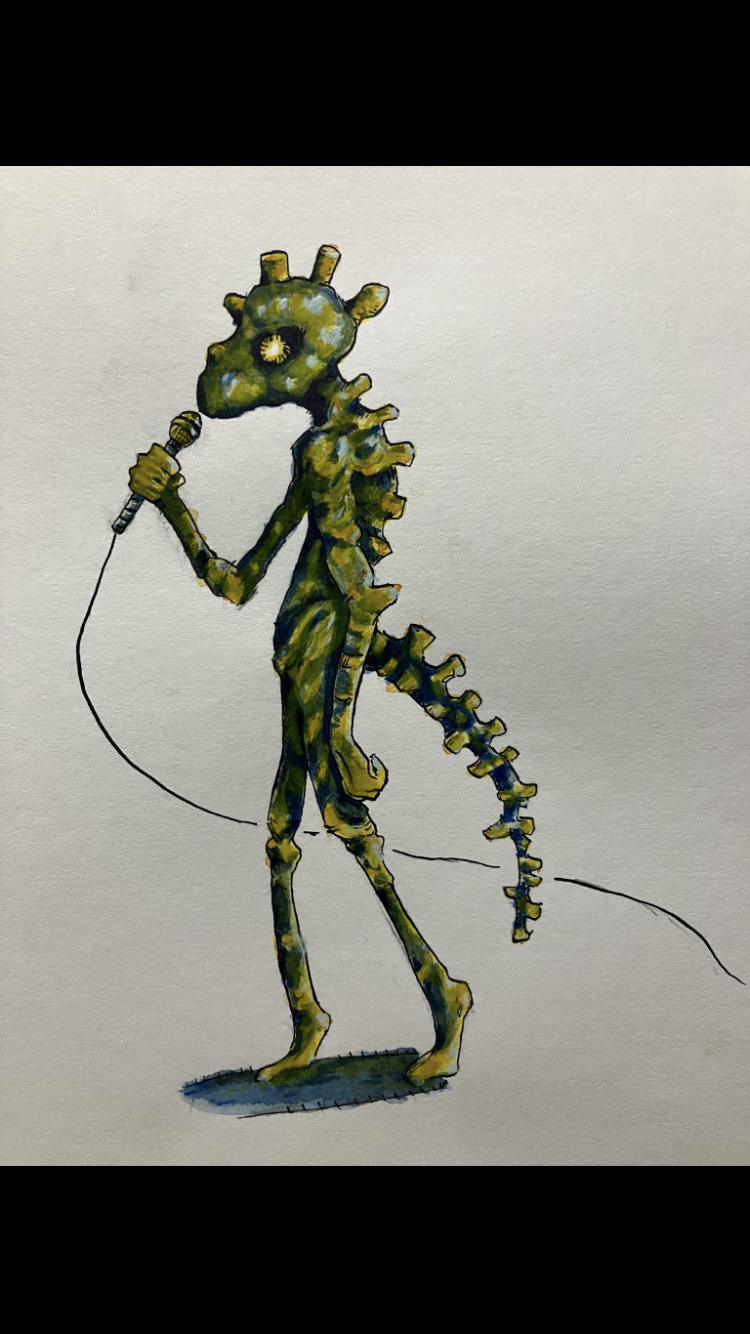
え?筋トレって毎日やらない方がいいんじゃなかったっけ!?
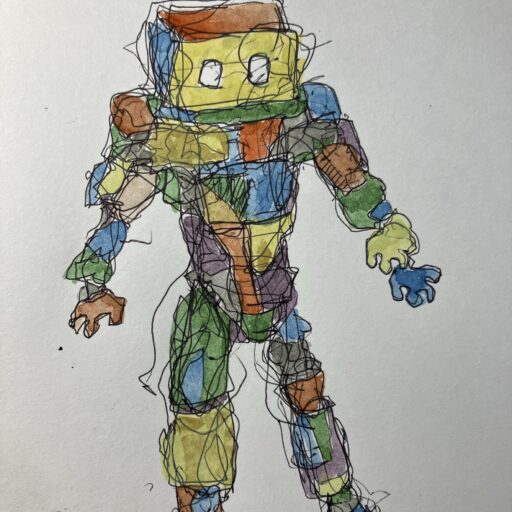
基本的にはその通り。
筋トレは毎日やらない方がいいんだけど、『週に何回筋トレをする』と決めて継続できてる?
筋トレを継続させる秘訣は、『筋トレを習慣化すること』です。
そして、筋トレを習慣化させるために効果的な方法は『3ヶ月毎日やること』(運動、早起き、禁煙などの体のリズムに関わる習慣化の期間は3ヶ月と言われています。)
私も継続率が高いとされている筋トレ・英語・ブログの3つを何年も継続していますが、継続が難しそうだと思うことは『最初の3ヶ月は毎日やる』事を取り入れています。
皆さんは筋トレを始める時に必ずこのキーワードを検索すると思います。
『正しい筋トレのやり方』、『筋トレのベストな頻度』
おそらく検索結果には、『筋トレは週に3日、1回に1時間程度やるのがベストです』と出るでしょう。
そして「週に3日がベストな筋トレの頻度ならば、月曜日、水曜日、金曜日に1日おきに筋トレしよう」と決意します。
そんなあなたに質問です。
そのやり方で続いたことはありますか??
だんだんと筋トレが継続できなくなる1週間の例を見てみましょう。
月曜:筋トレ
火曜:筋トレOFF
水曜:急な飲み会でOFF
木曜:残業が入ってOFF
金曜:残業と飲み会で疲れているのでOFF
土曜:筋トレ
日曜:OFF
30代は急な残業や飲み会、家族の行事で予定を変更せざる得ない状況がたくさん。筋トレできない日もあるでしょう。
ここで問題なのが、筋トレを始めて間もないうちは筋トレを計画通りに行う事ができないと「今日はいいかな」と妥協してしてしまいがちになる事です。
「今日はいいかな」が続くと「来週頑張ろう」になり、「筋トレなんてやっても効果が出ない」と最終的にジムを退会してしまいます。
これを防ぐために『3ヶ月は毎日継続する』を実践してみてください。
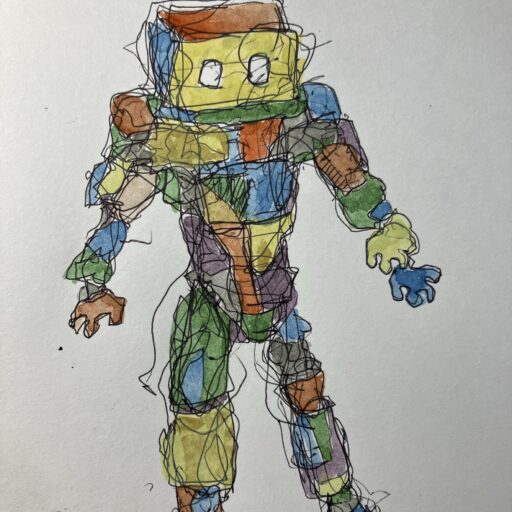
最初の3ヶ月は習慣化のための期間だと割り切って、効果は期待しないようにすると継続しやすくなります。
次は、モチベーションや疲れている時はどうするのか見てみよう
ズーニンの法則を活用する

ズーニンの法則はアメリカの心理学者レナード・ズーニン氏によって提唱されたもので、『何かを始める際に最初の4分間が極めて重要』であり、その後の活動の成功に大きく影響するとされています。
この法則は『初動4分の法則』としても知られており、物事を始めるとき、最初の4分を頑張ることで、その後の努力がスムーズに進むという考え方です。
皆さんも経験ありませんか?
最初は「めんどくせー!!」と思っていた事が、進めていくうちに「手が止まんなくなってきちゃったよー!」というアレです!!
これは『作業興奮』という機能によるもので、やる気がなくても作業を始めると、後からやる気が高まってくるというものです。
この『やる気が勝手に入っちゃう現象』は、脳の「側坐核(そくざかく)」という部分が関係しており、側坐核が刺激されるとドーパミンが分泌され
「始めはやる気出なかったけど、やる気出てきたー!!」
となっていくみたいです。
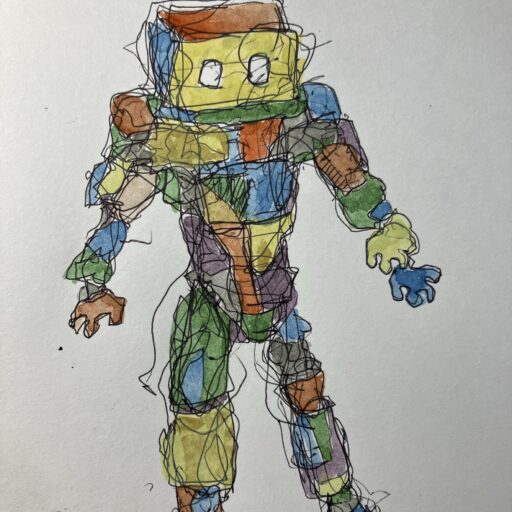
私は筋トレのやる気が出ない時もジムに行きます。
アップをしてもやる気が出ない場合は、本当に疲れているので帰りますが、アップが終わったらやる気になっている事が多いので、とりあえず行動するようにしています。
目標を低く設定する
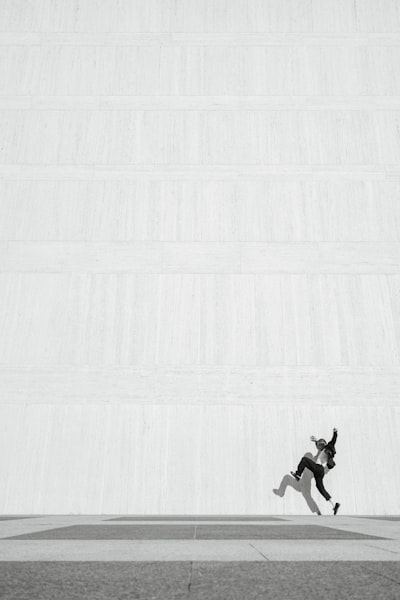
筋トレ継続の秘訣として、『目標を低く設定する』ことが成功への第1歩といえます。
モチベーションの維持に役立つ
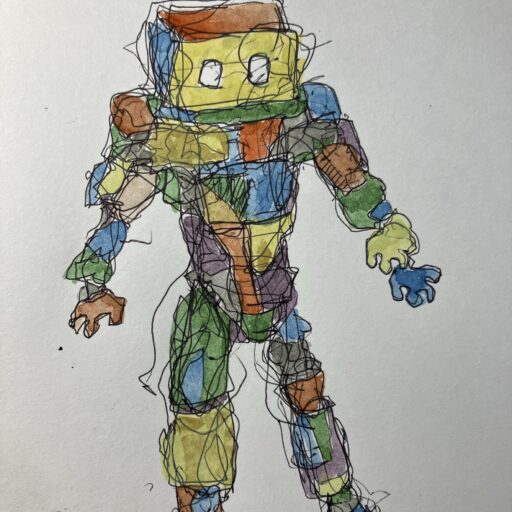
目標は低すぎていい
『スクワット10回』『腕立て1日10回』、『ジムに行く』これだけでもOK!
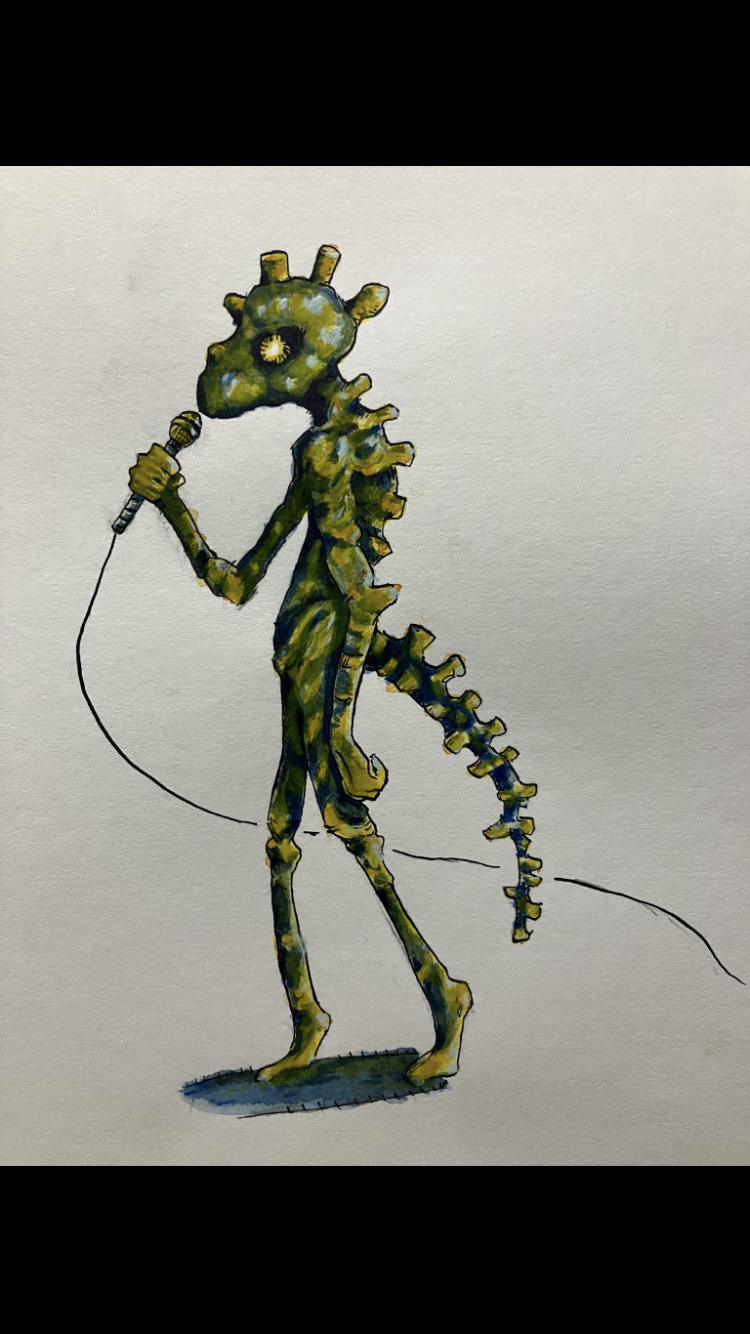
目標低すぎじゃない?
冒頭で伝えしましたが、行動を習慣化するためには3ヶ月必要だと言われています。
この3ヶ月で必要な事は目標を限りなく低く設定し、毎日その目標を達成していく事。
日々小さな目標を達成することは、成功体験を積み重ねる事ができ、大きな自信となり、この自信がさらにあなたの行動を変化させます。
「スクワット10回を1ヶ月続けたから、今月は20回にしてみよう」、「毎日20回続けられたから、ジムに入会しても続けられそうだ」と変化していきます。
あなたが目指しているのは短期的な変化ではなく、長期的に大きな変化です。
スクワット10回から始めたあなたは1年後、100kgのバーベルを背負ってスクワットをしているかもしれません。
ストレスにならない
トレーニングを始めてすぐの時はモチベーションが高いので、「毎日腹筋、腕立て、スクワット100回」「1日2時間トレーニングする」等と無理な計画を立ててしまいがち。
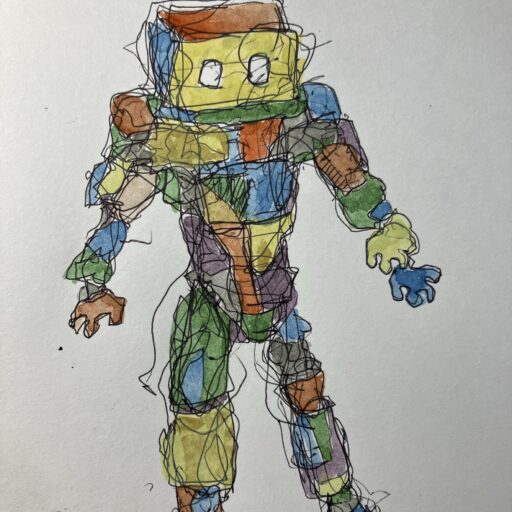
これトレーニングを継続できない理由第1位だと思う。
仕事から疲れて帰ってきた後に、腕立て伏せ100回なんてできます?やれてもせいぜい2日位なもんでしょう。
99%の人が挫折しますよ
高すぎる目標を設定すると、達成できなかった場合にストレスや不安を感じやすくなるというデメリットもあるので気をつけましょう。
低い目標は現実的でありストレスが少なく、目標達成の楽しさを感じられます。この感覚の積み重ねが、長期的な視点でのパフォーマンス向上に繋がるんですね。
私が行っていた具体的な目標設定
筋トレ:毎日ジムに行く → やる気が出ないなら帰る。
ジムにいけない日 → 腕立て、スクワット、背筋を30回
オンライン英会話:オンライン予約だけする。
5分前になってもやる気があったら続ける。やる気が出ないならキャンセル。
ブログ:5分間だけ文章を書く
やる気があるなら続ける、出ない場合はやめる
この3つはいずれも成果が見えにくく、成長を感じるのに時間がかかるのものばかりです。
またこの3つ取り組みは習慣となっている今でも続いており、少しやってやる気が出ない時はやらないと決めてます。
目標設定は低く設定し「そのうち身につくでしょう」くらいの気持ちで取り組むと、1年後には大きな力となっていますよ!!
時間を固定する

筋トレの習慣化には時間を固定することも効果的。
私の場合、平日は仕事が終わってそのままジムに行くか、一度家に帰ってすぐに荷物を持ってジムに行っています。
週末は午前中のうちにトレーニングを終わらせるのがルーティーンとなっています(週末は午前中のうちにトレーニングが終わらないと一日気持ちが悪い)
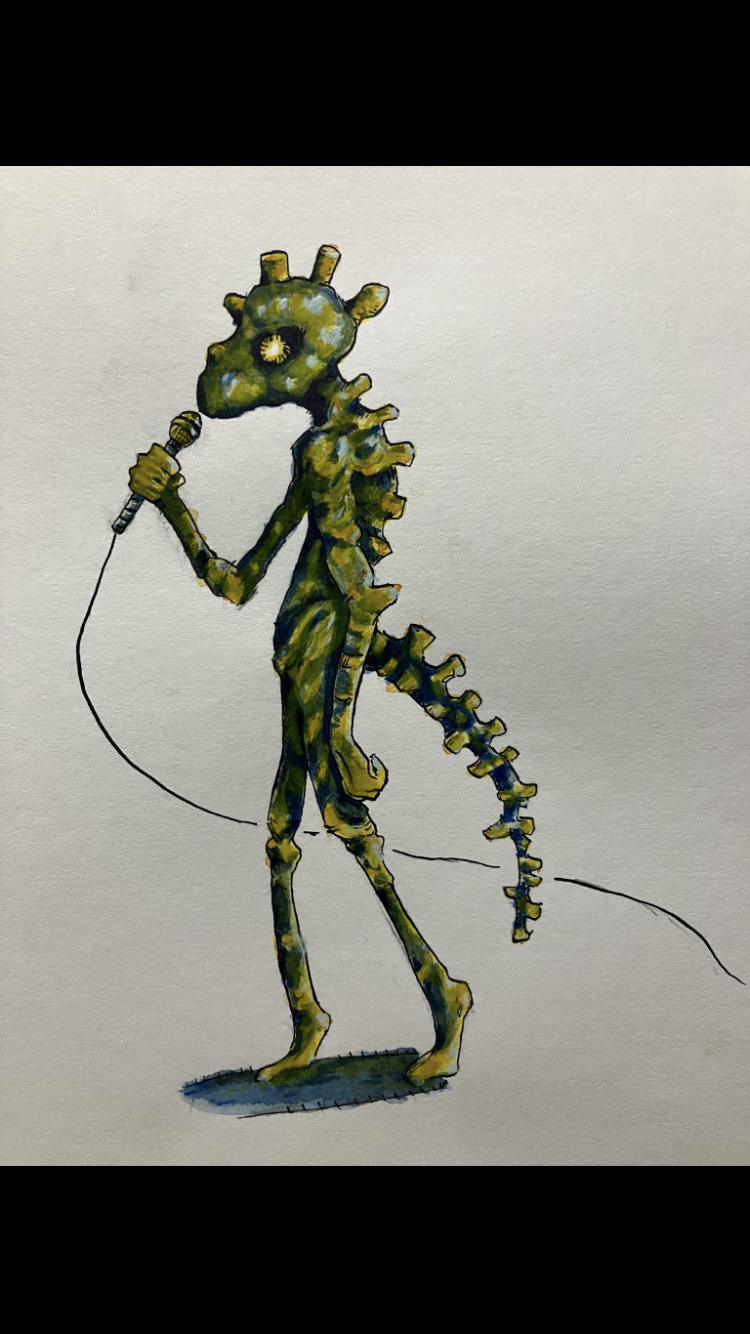
トレーニングの時間を固定した方がいいのは分かってるんだけど、ジムに行く時間をなかなか確保できないんだよねー
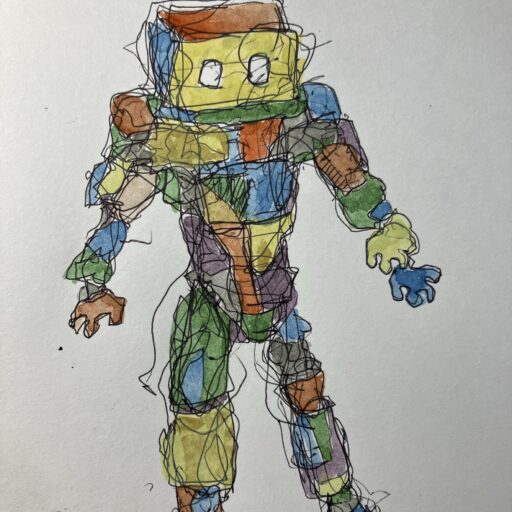
トレーニングの時間を確保できない時は、朝の時間にジムに行くのはどうかな?
朝の時間に筋トレを行うメリットは以下の通り
- 代謝の促進
- 集中力の向上
- 習慣化のしやすさ
- 心身のリフレッシュ
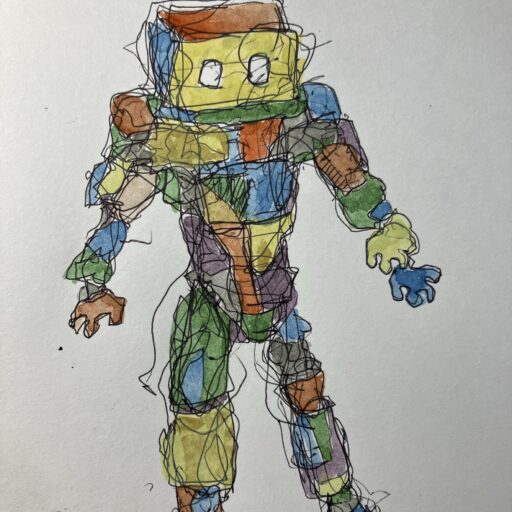
1個ずつ見ていこう!
代謝の促進
朝の筋トレは、身体の代謝を向上させ、一日を通じてカロリーの消費を増やす効果があります。
これは、朝の運動によって交感神経が刺激され、代謝が活性化されるためです。
新陳代謝を上げることで、エネルギーを消費しやすい体を作り、太りにくい体質に近づくことが可能です
集中力の向上
朝の筋トレは、脳を目覚めさせ、仕事や勉強への集中力を高めるのに役立ちます。
特にストレッチや軽い運動を行うことで、血流が良くなり、よりクリアな思考を促します
習慣化の容易さ
朝の時間帯に運動を取り入れると、他の予定に影響されにくく、習慣化しやすくなります。
朝のトレーニングは、忙しい日々においても一貫して続けやすいという利点があります。

朝は残業や急な飲み会などがないから、行動を習慣化するのにベストなタイミング!
心身のリフレッシュ
朝に運動することで、身体が活性化し、気分が良くなる効果があります。
筋肉を動かすことで脳内のエンドルフィンが分泌され、ストレスの軽減にも効果的です。
また、夜の睡眠の質が向上することがあります。体がリラックスして、深い睡眠を得やすくなるため、翌日のエネルギーも回復しやすいです。
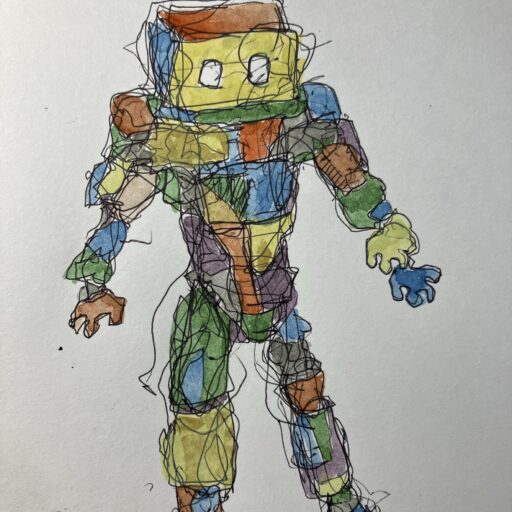
私は朝のウォーキングが大好き!!
朝って空気が澄み切っていて静かなので、歩いてるとリフレッシュできるんですよねー
※朝トレの注意点
朝に筋トレを行う際は、体温が低い状態で行うため、必ず十分なウォーミングアップを行い、けがを防ぐことが大切です。
トレーニングは最低でも30分程度を目安にし、早急な高負荷トレーニングは避けることが推奨されています。
また、何も食べずに空腹状態でのトレーニングは避けるべきです。
空腹状態でのトレーニングは脂肪を燃やしてエネルギーを作ると言われていますが、脂肪と同時に筋肉も消費されてしまい基礎代謝が低下してしまいます。
空腹でトレーニングすると糖質不足から集中力が落ちて力が入らず、パフォーマンス低下につながります。トレーニング前には吸収のいいバナナやプロテインを摂取し、体に栄養を入れてトレーニングをするようにしましょう。
記録をつける
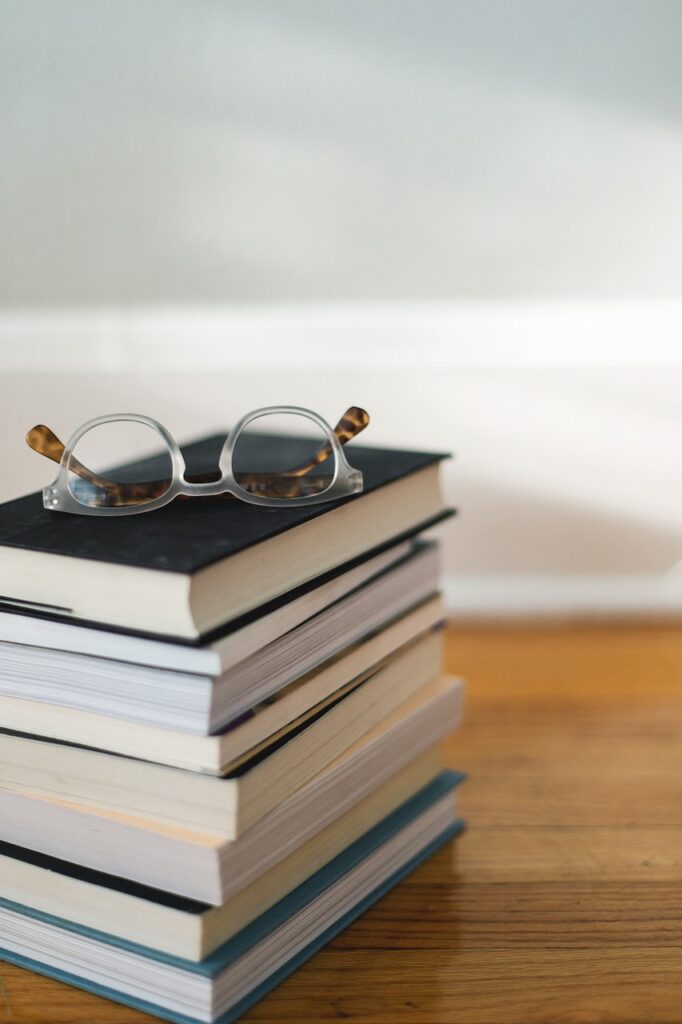

トレーニング記録は必ずつけようにしましょう!!
記録を取ることには、以下のメリットがあります
- トレーニングの効果を高める
- 進捗の可視化
- トレーニングの改善点が見つかる
- モチベーションの維持
- オーバートレーニングの防止
トレーニングの効果を高める
トレーニングにおいて効果を最大にするためには、負荷を少しずつ高めていく『漸進性の過負荷の原則』にのっとりトレーニングを継続していく必要があります。
計画的に負荷を高めていくためには『何を、何キロで、何回やったか』を把握できていないと自己満足なトレーニングになってしまいます。
トレーニング記録をとっていると「前回はこれくらいでやったはず」と「疲労感」や「パンプ感」を指標にトレーニングする事がなくなります。
またトレーニング内容を記録することにより、次のトレーニングで『何を・何キロで・何回』をやれば良いのかがすぐにわかり、具体的なトレーニングの指標となります。
進捗の可視化
トレーニング記録をつけておくと、継続している期間や自分の成長を数字として見ることができます。
過去の自分との比較(持てるようになった重さや回数、セット数などの変化)を確認することで、達成感を感じやすくなります。

トレーニング効果がなかなか見えない時は過去の自分と比較してみよう!
必ず成長してるはず!!
トレーニングの改善点を見つけやすい
記録をつけていくと、自分の弱点や課題が明確になります。
記録をしておくと過去のトレーニングを振り返る事ができるので、特定の部位の筋力が伸びていない場合、その部位にフォーカスしたトレーニングを行う事ができます。
モチベーションの維持
記録をつけると、トレーニングに対するモチベーションが下がりにくくなります。
物事が途中で続かなくなった『期間が空きすぎてどうでも良くなった』という事はありませんか?
記録をとっている場合と、とってない場合の違いはこのようになります。
記録をとっている場合
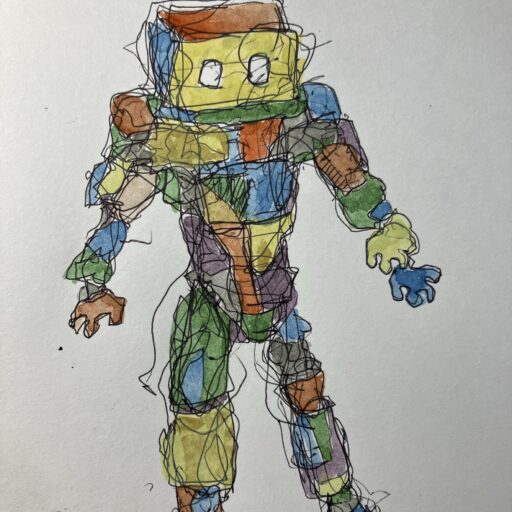
1週間休んだな!!
体と心の疲労も抜けたからまた思いっきり筋トレ頑張ろう!!
記録をとってない場合

トレーニングできない日が続いてしまった…
今回は結構続けられてたのに、また今年もダメだった…orz
空いた期間を明確にしておくと、その期間に意味を持たせる事ができるようになるのです。←これめちゃくちゃ大切!!
オーバートレーニングを防ぐ
記録をつけるメリットに、オーバートレーニングを防ぐ効果もあります。
トレーニングが楽しいとトレーニングオフの日を設定せずにトレーニングしがち。
記録を取ることで、負荷や頻度が明確になるため、ディロード期間を入れるタイミングを設定しやすくなります。
これにより、過剰なトレーニングを避け、リフレッシュした状態でトレーニングを再開する事ができます。
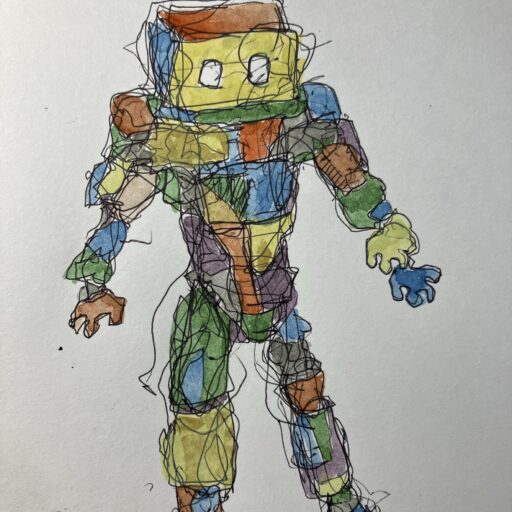
トレーングを休むことに罪悪感はありませんか?
記録をつけると戦略的にOFFを入れる事ができるのでトレーニングの効果を高める事ができます。
まとめ
筋トレ継続のコツは4つ
- 3ヶ月間は毎日行う
- 目標を低く設定する
- 時間を固定する
- 記録をつける
筋トレ継続のコツとして4つまとめましたが、このコツは筋トレだけでなく新しい事を始める時に共通して効果があります。
私自身、これまでにブログ継続を2回挫折しており、今回は3度目のチャレンジをしています。
今回はこの4つを全て行ってブログを継続し、習慣化する事ができました。
習慣化するまでが大変ですが、習慣化してしまうと歯磨きのように『やらないと気持ち悪い』状態になります。
習慣化は本当に小さい1歩から。
ベビーステップ。
小さい一歩を継続していきましょう。
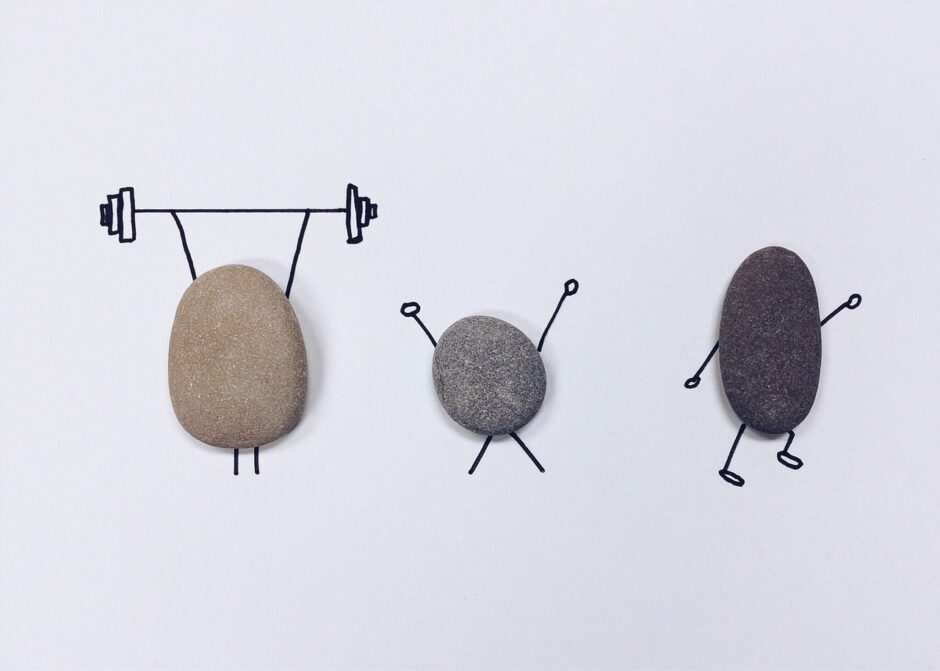






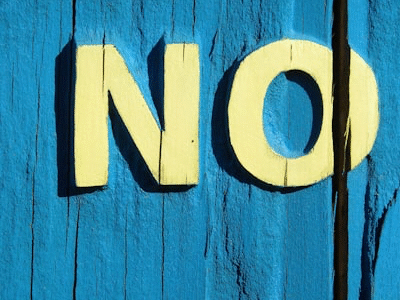



[…] 筋トレに至っては、、筋トレ1年間の継続率は4%ととても低い数値であることが判明。 […]